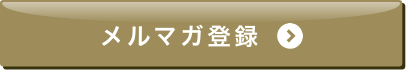人事制度の実効性を高める評価運用とは
人事コンサルタント 古崎 篤
人事制度の制定/改定のコンサルティング支援において、課題把握のために行う従業員アンケートで上位にくる項目のひとつが、「評価に対する懸念」です。
「上司が正しく評価できるのか?」
「公平・公正な評価が本当にできるのか?」
「適切に評価できる基準があるのか?」
このような声が多く寄せられ、従業員側が評価に対していかに不安を抱いているか改めて認識するとともに、会社側としては、その処方箋となる施策を、新たな制度設計と運用フローの中に実装しなくてはなりません。
一般に、人事制度は「等級制度」「報酬制度」「評価制度」の3つの制度の有機的な集合体として構成されています。
例えて言えば、前2つに関しては人事制度の仕組みとしての「ハード」的要素が色濃いのに対し、評価制度は評価結果を導き出して昇格や昇給・賞与に反映するという、言わば人事制度を動かすための「ソフト」の位置付けにあります。
よって、いかに優れたハード(等級制度や報酬制度)を整えたとしても、ソフト(評価制度)の運用が正しく行われ、評価を受ける従業員の信頼に足るものでなければ、人事制度全体としての実効性は高まらず、期待する効果も得られません。
人事制度の実務では、「設計以上に運用こそが重要である」とよく言われます。
特に評価制度においては、制度をあるべき形に設計するだけでなく、それを土台とした適切な運用ができる状態までスコープする必要があります。
評価制度の運用を向上させる方法論やテクニックは様々ありますが、従業員の評価への納得感を高める根本要素を突き詰めると、以下2点になると思われます。
(併せて、それぞれに対する主な施策を例示します)
①評価の「仕組み」と「基準」が明確であること
②「評価者」に対する信用と信頼があること
【①の施策例】
●目標達成評価/成果評価の場合・・・具体的かつ計測可能な形で目標設定する(=いわゆる「SMARTの法則」を踏まえる)
●行動評価/プロセス評価の場合・・・評価項目となる行動基準を明確化する。加えて、等級ごとに行動基準を書き分け、上下等級間での違いが比較できるようにする
●上記のように客観性を持った目標設定や行動基準のもと、個人としての目標への到達度合いや行動の発揮度合いを測る(=絶対評価)
●公平かつ公正な評価実施や処遇決定のプロセスとして、目標設定/評価結果についての合議による擦り合わせ、および、フィードバック面談の定期化と運用改善 など
【②の施策例】
●評価者側の十分な制度理解を通じて、評価者が自社の評価制度の意義と仕組みについて自分の言葉で部下に伝えられる
●期中における部下の行動観察を十分に行い、評価実施に必要な行動事実の記録と収集を行う
●評価者が目標設定/フィードバック時の面談の型を理解し、面談スキルを向上させる など
以上はあくまでも施策の一例に過ぎませんが、冒頭にお示しした「評価に対する懸念」への一定の回答になっていることがお分かりいただけるかと思います。
繰り返しになりますが、評価制度においては、運用まで目を向ける必要があります。
制度の設計/改定や評価者研修にとどまらず、目標設定や評価実施のプロセス、面談のあり方に至るまで、「面」による継続的な運用フォローを行うことが、評価に対する従業員の不安を払拭し、人事制度自体の有意味感の醸成に繋がるのです。
皆様もぜひ、ご自身の会社の評価運用のあり方について、この視点をもって見直してみてください。